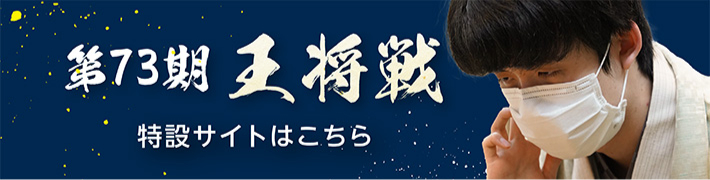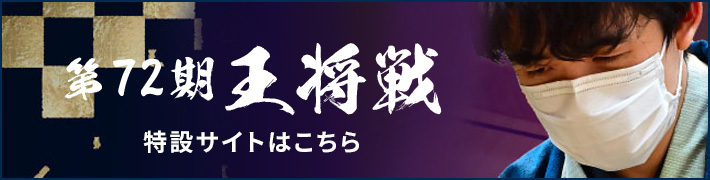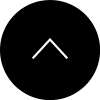防衛
藤井王将が見事に王将戦4連覇。この結果、タイトル獲得通算28期で、谷川浩司17世名人を抜いて歴代単独5位となりました。
七番勝負

永瀬九段は序盤の研究が深く、中終盤も気が付きづらい好手が多い印象です。2日制での対局は初めてで、楽しみな気持ちもあります。
一手一手深く考えて、充実した内容の将棋が指せるよう、がんばりたいと思います。


藤井王将とのタイトル戦は今回で4度目になります。
藤井王将とは初めての2日制でのタイトル戦となりますので手探りの部分はありますが、しっかりと準備をして挑みたいと思います。
対局結果
七番勝負
闘いの舞台である王将戦七番勝負。緊張感溢れる中で味わう食事は、思考を巡らせる棋士にとって必要不可欠なエネルギー源。そんな彼らが口にした”勝負めし”をご紹介します。
開催概要
ALSOK杯 第74期 王将戦
全棋士で行う棋戦。一次予選・二次予選をトーナメントで行い、その勝ち上がり者とシード棋士4人でリーグ戦を行います。
王将とリーグ優勝者が、例年1月から3月にかけて七番勝負を行います。
持ち時間は、一次予選・二次予選が3時間、挑戦者決定リーグが4時間、王将戦七番勝負が2日制(封じ手採用)の8時間です。
日程
- 一次予選(2024年1月〜6月)
- 持ち時間
3時間 - 開始時間
10:00 - 昼食休憩
12:00
〜12:40 - 結果を見る
- 二次予選(2024年6月〜8月)
- 持ち時間
3時間 - 開始時間
10:00 - 昼食休憩
12:00
〜12:40 - 結果を見る
- 挑戦者決定リーグ(2024年9月〜12月)
- 持ち時間
3時間 - 開始時間
10:00 - 昼食休憩
12:00
〜12:40 - 結果を見る
- 七番勝負(2025年1月〜3月)
- 持ち時間
8時間
(2日制) - 開始時間
9:00 - 昼食休憩
12:30
〜13:30
七番勝負対局日程・開催場所
- 日程
- 場所
- 第1局
- 1月12、13日(日、月祝)
- 静岡県掛川市
「掛川城 二の丸茶室」
- 第2局
- 1月25、26日(土、日)
- 京都府京都市
「伏見稲荷大社」
- 第3局
- 2月5、6日(水、木)
- 東京都立川市
「オーベルジュ ときと」
- 第4局
- 2月15、16日(土、日)
- 大阪府高槻市
「摂津峡花の里温泉 山水館」
- 第5局
- 3月8、9日(土、日)
- 埼玉県深谷市
「旧渋沢邸『中の家(なかんち)』」
- 第6局
- 3月21、22日(金、土)
- 佐賀県三養基郡上峰町
「大幸園」
- 第7局
- 3月29、30日(土、日)
- 栃木県大田原市
「ホテル花月」
特別協賛

「王将戦」とは
「王将戦」は、1950年に創設され、翌51年からタイトル戦となりました。
現在8大タイトル戦の中で名人戦に次ぐ歴史を持つ伝統と格式のある棋戦です。
創設当初は「三番手直り」制で3連勝した場合は次局、平手でなく駒落ち(香落ち)で対局を行う独自の制度があり、第4期で大山王将が挑戦者の松田八段に1勝1敗2千日手後に3連勝し、タイトル戦での「駒落ち」対局が実現しました。
規定の回数以上を獲得した場合に与えられるタイトルの永世称号(永世王将)ですが、王将戦は「通算10期獲得」とハードルが高く、これまで大山康晴・羽生善治の2名のみとなっています。
大山康晴のタイトル保持者としての過去最高齢記録(第32期王将戦 七番勝負 出場時の59歳11ヶ月)や、社会的現象として話題にもなりました羽生善治のタイトル全冠制覇(当時7つのタイトルを独占/第45期王将戦)も、この王将戦で達成されました。
また、対局終了後や翌日に撮影する写真はインパクトのあるものが多く、当初から多くの話題と注目を集め、楽しみの1つとしてファンに親しまれています。

王将戦への熱い想い
将棋の歴史は古く平安時代にはその原型となるものがあったとされており、現在の「将棋」となって以来、駒の動かし方など基本的なルールは変わっていないにもかかわらず、対局者の研究により次々と新たな戦術が生み出され続けています。
あらゆる世代の方に親しまれている将棋は、バランスの取れた「攻め」と「守り」が重要ですが、当社が主業務にしている「警備」の世界も万全な「守り」だけでなく、近年では、人による警備からAI等の先端技術を活用した「攻め」のセキュリティに進化を遂げています。
また、将棋の世界の対局相手に示す敬意や負けた側が自ら宣言する高潔さに、当社創業以来の精神である「ありがとうの心」と「武士の精神」との親和性を感じ、この度の特別協賛に至りました。
当社が特別協賛をさせていただく2021年4月からは、本棋戦に当社の冠が付き「ALSOK杯王将戦」となりました。
挑戦者決定リーグ参加者
動画
インタビュー
- 日本将棋連盟 会長 羽生善治
- 1970年9月27日生まれ。
埼玉県所沢市出身。
2023年6月から日本将棋連盟会長を務める。
長期にわたって将棋界のトッププレイヤーとして活躍されていらっしゃいますが、その継続的な成功の秘訣は何だと思いますか。
どんな時も現状に立ち止まらずに挑戦を続けて行くことだと考えています。
これから将棋を始めようとする人々にアドバイスをお願いします。
ルールを覚えた後は基本の攻めと守りの形を覚えて、そこからは自由に指してください。
長いキャリアの中で、印象に残る対局等がありましたら教えてください。
デビュー間もないころに明治生まれの小堀九段と対戦をしたことです。感想戦が終わったら朝になっていました。
- 小堀清一 九段
- 小堀清一 九段
1912年(明治45年)
~1996年(平成8年)
神奈川県横浜市出身。1929年(昭和4年)奨励会入り。1986年(昭和61年)、15歳の羽生善治四段(当時)と対戦、熱戦は午前1時まで続き(羽生勝利)、感想戦が終わったのは翌朝午前8時であった。小堀九段は、研究熱心で知られ、腰掛け銀定跡の基礎を築いた。羽生との対局においても、戦型は、相掛かり腰掛け銀であった。
写真引用:日本将棋連盟ホームページ
AIの登場は将棋界のトレンドにどのような影響を与えたとお考えですか?
人間の個性とは何かが問われる時代だと思っています。
対局中の食事ですが、どのようなものをよく召し上がられますか?
軽めに麺類を注文することが多いです。ただ、昼と夜の食事がある場合はどちらかはお米を食べます。
将棋の基礎知識
新しく将棋に興味を持った方でも王将戦の観戦をより楽しめるよう、将棋の基本ルールや解説などでよく耳にする用語を紹介します。
-
- 駒の動き
- 各駒(王将、飛車、角行、金将、銀将、桂馬、香車、歩兵)の動き方。
- 駒の動きについて 【日本将棋連盟ページ】
-
- 持ち駒
- 相手の駒を取った後、自分の駒として使える。
-
- 成り
- 特定の駒が敵陣に入ったときに、強力な駒に変わる。
-
- 千日手
- 同じ局面が4回繰り返されると引き分けになる。
-
- 持将棋
- 両者の持ち駒と盤上の駒の合計点が24点以上で引き分けになる。
-
- 二歩
- 同じ縦列に2枚の歩兵を置くことが禁止されている。
-
- 打ち歩詰め
- 持ち駒の歩兵を使って相手の王将を詰ませることが禁止されている。
-
- 矢倉(やぐら)
- 王将を守るための堅固な囲いの一つで、初心者にも学びやすい基本的な戦法。
-
- 美濃囲い(みのがこい)
- 主に振り飛車戦法で使われる囲いで、バランスの良い守りを提供します。
-
- 穴熊(あなぐま)
- 非常に堅固な囲いで、守りを重視する戦法。
-
- 振り飛車(ふりびしゃ)
- 飛車を左側に振る戦法で、相手の攻撃をかわしつつ反撃を狙います。
-
- 居飛車(いびしゃ)
- 飛車を初期位置に置いたまま戦う戦法で、攻撃力が高い。
-
- 角交換(かくこうかん)
- 角行を交換することで局面を複雑にし、相手のミスを誘う戦法。
王将戦七番勝負 対局史
王将戦では、多くの名勝負が繰り広げられてきました。
大山康晴十五世名人は通算20期、王将位を獲得。また、羽生善治九段(将棋連盟会長)も第45期の王将戦で勝利し、史上初の全七冠(当時)制覇を成し遂げた後、通算12期にわたり王将位を獲得しました。両者とも通算10期在位を達成し「永世王将」の資格を獲得しています。
最近では、藤井聡太王将が注目を集めています。藤井王将は第71期(2022年)から王将位を保持しており、その若さと実力で将棋界をリードしています。
王将戦の歴史を振り返ると、多くの名棋士たちがしのぎを削り、将棋の魅力を伝えてきました。
昭和(第1回〜第38期)
- 初代王将を決める対–局で、升田八段が木村名人を破り、初代王将に輝きました。第6局で升田八段が対局を拒否する「陣屋事件」があったことでも有名です。
- 升田八段が「名人に香車を引いて勝つ」という伝説的な対局です。升田八段は大山名人に対し、香車落ちのハンデをつけて勝利。この勝利は将棋界に大きな衝撃を与えました。
- 大山王将が中原二冠を破り、通算20期目の防衛を達成しました。大山王将は1勝3敗から史上2度目の大逆転防衛に成功したことが話題となりました。
- 中村修六段が中原王将を破り、23歳にして史上最年少王将となりました。この記録は、後に藤井聡太四冠(当時)が2022年に19歳で王将位を獲得するまで36年間もの間、破られることがありませんでした。
- 第1回 昭和 25年 木村 義雄 4 - 2 丸田 祐三 第1回は一般棋戦として開催され、翌年より第1期王将戦としてタイトル戦になりました。
- 升田 幸三,4 - 1,木村 義雄
- 大山 康晴,4 - 3,丸田 祐三
- 大山 康晴,4 - 2,升田 幸三
- 大山 康晴,4 - 1,松田 茂行
- 升田 幸三,3 - 0,大山 康晴
- 升田 幸三,4 - 2,大山 康晴
- 大山 康晴,4 - 3,升田 幸三
- 大山 康晴,3 - 0,高島 一岐代
- 大山 康晴,4 - 2,二上 達也
- 大山 康晴,4 - 2,二上 達也
- 大山 康晴,3 - 0,加藤 一二三
- 二上 達也,4 - 2,大山 康晴
- 大山 康晴,3 - 0,二上 達也
- 大山 康晴,4 - 1,加藤 博二
- 大山 康晴,4 - 3,山田 道美
- 大山 康晴,4 - 1,加藤 一二三
- 大山 康晴,4 - 2,加藤 一二三
- 大山 康晴,4 - 0,内藤 國雄
- 大山 康晴,4 - 1,二上 達也
- 大山 康晴,4 - 3,中原 誠
- 大山 康晴,4 - 3,有吉 道夫
- 中原 誠,4 - 0,大山 康晴
- 中原 誠,4 - 2,米長 邦雄
- 中原 誠,4 - 3,米長 邦雄
- 中原 誠,4 - 1,有吉 道夫
- 中原 誠,4 - 2,大山 康晴
- 中原 誠,4 - 2,有吉 道夫
- 加藤 一二三,4 - 1,中原 誠
- 大山 康晴,4 - 2,加藤 一二三
- 大山 康晴,4 - 1,米長 邦雄
- 大山 康晴,4 - 3,中原 誠
- 米長 邦雄,4 - 1,大山 康晴
- 米長 邦雄,4 - 1,森 雞二
- 中原 誠,4 - 1,米長 邦雄
- 中村 修,4 - 2,中原 誠
- 中村 修,4 - 2,中原 誠
- 南 芳一,4 - 3,中村 修
- 南 芳一,4 - 0,島 朗
平成(第39期〜第68期)
- 羽生六冠が史上初の七冠制覇を目指した対局で、谷川王将がその挑戦を阻止しました。この対局は阪神淡路大震災の直後に行われ、谷川王将が逆境を乗り越えて勝利したことから、多くの人々に感動を与えました。
- 羽生六冠が史上初の七冠を達成した対局です。前期の敗戦から王将以外に保持していた六冠の防衛に全て成功して2期連続で谷川王将へ挑んだ勝負を制し、将棋界に新たな歴史を刻みました。
- 米長 邦雄,4 - 3,南 芳一
- 南 芳一,4 - 2,米長 邦雄
- 谷川 浩司,4 - 1,南 芳一
- 谷川 浩司,4 - 0,村山 聖
- 谷川 浩司,4 - 2,中原 誠
- 谷川 浩司,4 - 3,羽生 善治
- 羽生 善治,4 - 0,谷川 浩司
- 羽生 善治,4 - 0,谷川 浩司
- 羽生 善治,4 - 1,佐藤 康光
- 羽生 善治,4 - 1,森下 卓
- 羽生 善治,4 - 0,佐藤 康光
- 羽生 善治,4 - 1,谷川 浩司
- 佐藤 康光,4 - 2,羽生 善治
- 羽生 善治,4 - 0,佐藤 康光
- 森内 俊之,4 - 2,羽生 善治
- 羽生 善治,4 - 0,森内 俊之
- 羽生 善治,4 - 3,佐藤 康光
- 羽生 善治,4 - 3,佐藤 康光
- 羽生 善治,4 - 1,久保 利明
- 羽生 善治,4 - 3,深浦 康市
- 久保 利明,4 - 2,羽生 善治
- 久保 利明,4 - 2,豊島 将之
- 佐藤 康光,4 - 1,久保 利明
- 渡辺 明,4 - 1,佐藤 康光
- 渡辺 明,4 - 3,羽生 善治
- 郷田 真隆,4 - 3,渡辺 明
- 郷田 真隆,4 - 2,羽生 善治
- 久保 利明,4 - 2,郷田 真隆
- 久保 利明,4 - 2,豊島 将之
- 渡辺 明,4 - 0,久保 利明
令和(第69期〜第73期)
- 藤井四冠が渡辺王将を破り、史上最年少で王将位を獲得しました。この対局は、藤井四冠の圧倒的な強さと若さが際立ちました。
- 羽生九段が藤井王将に挑戦し、両者が交互に勝利する激戦の末、藤井王将が4勝2敗で初防衛を果たしました。この対局は「歴史的名勝負」として語り継がれています。
- 渡辺 明,4 - 3,広瀬 章人
- 渡辺 明,4 - 2,永瀬 拓矢
- 藤井 聡太,4 - 0,渡辺 明
- 藤井 聡太,4 - 2,羽生 善治
- 藤井 聡太,4 - 0,菅井 竜也