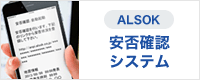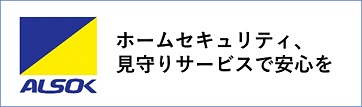瑕疵担保責任(契約不適合責任)とは?瑕疵と見つけるポイント、注意点を解説

住宅購入を検討中のタイミングなど、不動産の売買を考えている方がよく耳にする言葉の1つに「瑕疵担保責任(契約不適合責任)」が挙げられます。
この記事では、不動産売買の際にとても重要な責任事項となる瑕疵担保責任について、その詳細を分かりやすくご紹介します。
瑕疵担保責任(契約不適合責任)とは

瑕疵担保責任とは、不動産売買において売主に課せられる重要な責任事項です。ここでは、この「瑕疵」とは何を指し、それに対し売主がどのような責任を負うこととなるかについてご紹介します。
不動産物件における瑕疵とは
瑕疵は「かし」と読み、住宅など建物の傷や不具合、欠陥などを指す言葉です。この場合で言う建物の瑕疵は、目に見える物理的な傷や破損にとどまりません。事前に通知されていた建物の性能や機能、居住条件、過去の自殺や事故死に関する情報、法律上の規制が実際と違っていたなど「建物が本来あるべき要件を満たしていないこと」はすべて「瑕疵」にあたります。
「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に
瑕疵担保責任は、2020年4月の民法改正によって「契約不適合責任」へ変更されました。内容的にも従来の瑕疵担保責任とは変わった部分があります。ただし不動産業界などでは現在でも通称として瑕疵担保責任の呼び名が用いられるケースが少なくありません。
瑕疵担保責任とは「引渡し後に分かった瑕疵に対し負うべき責任」
買主は建物の状態や居住条件などを伝えられ、納得の上で売買契約を結んでいます。しかし建物の引渡し後、建物の状態・状況が契約時に伝えられた通りでないケースも少なくありません。その瑕疵に対し売主が一定期間負うべき責任が「瑕疵担保責任(契約不適合責任)」です。
先にも述べましたが、建物の瑕疵は目に見える破損や不具合だけではありません。住み始めてから分かってくる「隠れた瑕疵・見えない瑕疵」も数多く挙げられます。次の項目では、それらの隠れた瑕疵についてもご紹介します。なお契約不適合責任では、瑕疵が隠れている(見えない)かどうかは問題にならず、契約目的に合っていなければ責任が発生します。
隠れた瑕疵とは

見たり触ったりしただけでは分からない「隠れた瑕疵」も、住宅などの建物には現れることがあります。隠れた瑕疵として、主に以下のような状態・状況があります。
物理的瑕疵
居住しているうちに雨漏りが見つかったり、シロアリ被害を受けていることが分かったりすると物理的瑕疵の1つに挙げられます。また、地盤沈下や危険物が埋蔵されていること、耐震基準の不適合も物理的瑕疵に該当します。
法律的瑕疵
居住条件そのものに問題はなくても、構造上の安全基準が満たされていなかったり、設置義務のある防災設備が設置されていなかったりなどして建築基準法、都市計画法、消防法などの法令に抵触している場合は法律的瑕疵となります。法律、条例などにより建築規制が及ぶので再建築ができないケースなどでも法律的瑕疵となる可能性があります。
心理的瑕疵
その住宅の建物や敷地で過去に殺人事件や住人の自殺などが発生している場合は、「心理的瑕疵のある物件」としてみなされる場合があります。心理的瑕疵は、「通常人が住みたくないと感じるような出来事が過去に起こった物件」に認められます。
過去に事件や事故が起こった場合、知っていたら契約しなかった人も多いでしょうし、契約するとしても代金を減額していたでしょう。それにもかかわらず売主が告げなかったために「瑕疵」となるのです。
暴力団やカルトなど、反社会的勢力の拠点が建物近隣にあるケースも心理的瑕疵にあたる場合があります。知っていながら売主がその事実を説明しないと、解除や損害賠償など契約不適合責任を問われる要因となります。
環境的瑕疵
周辺環境が悪い問題を「環境的瑕疵」と言います。たとえば建物の近隣にごみ処理施設や騒音を出す施設などが所在しているケースなどです。このような環境面での問題点を売主が把握しており、且つ買主にそれを伝えていなかった場合には、瑕疵となる可能性が高いと考えてよいでしょう。
瑕疵担保責任(契約不適合責任)の範囲と期間

瑕疵担保責任(現在の契約不適合責任)の責任範囲と期間についても買主側の視点から見ていきましょう。
民法
従来、瑕疵担保責任において買主は「損害賠償」または「契約無効」の請求のみが可能でした。2020年に民法が改正され「契約不適合責任」となって以降はその2つに加え、「追完請求(不足分の引渡し)」と「代金の減額請求」も可能となっています。
追完請求とは問題がある場合に修繕などの対応を請求すること、不足分の引き渡しとは、数量が規定されているのに足りていない場合に、不足しているものの引き渡しを要求することです。
買主はまず追完請求を行い、その請求内容が期間内に履行されなかった場合に代金の減額を請求するという順序で、売主への対応を求めることとなります。
また、契約不適合責任の期間にも制限があります。買主は、契約不適合(瑕疵)を知ってから1年以内に売主への責任追及の通知をしなければ権利を失うため、瑕疵に気づいたら早期の対処が必要です。
また1年以内に通知したとしても、その後売主に請求することなく5年または10年が経過してしまうと買主の権利は時効によって失われてしまいます。そのため、買主が瑕疵を知ってから5年以内に、契約不適合責任による建物修繕や不足分引き渡しなどの具体的な対応を売主に請求することが必要です。
さらに、買主が瑕疵に気づかないままでも、引渡しから10年が経過すると売主に対応を求める権利を失ってしまいます。(買主の通知義務+補完請求→失権効のルール)
宅地建物取引業法
売主が宅地建物取引業者(不動産会社)である場合は、宅地建物取引業法により責任義務期間は「物件の引渡し日から2年 」を下限としています。これを下回るような買主にとって不利になる特約はできません。つまり宅建業者の契約不適合責任を制限するとしても、最低限「引渡しから2年」は買主の権利を保障しなければならないのです。
なお民法の原則により、売主が宅建業者から購入した場合であっても、買主は契約不適合要因を知ってから1年以内に通知をしなければなりません。
品確法
売買する物件が新築住宅の場合は、品確法に基づき建物の基本構造部分の瑕疵担保責任(契約不適合責任)を「引渡しから10年以上負う」ことと定められ、契約によって20年まで延長が可能となっています。
売主にあたるハウスメーカーなどでは、瑕疵担保保証期間を10年ではなく20年に設定しているケースも少なくありません。ただし、5年~10年ごとに売主が定期点検を行い、その結果で改修を行うことを条件としている場合が一般的です。保証期間の延長は基本的に改修などの条件付き契約となるため、買主はその出費もよく考えて延長を検討する必要があります。
なお瑕疵が分かってから1年以内に買主側が通知しなければならないのは、民法の一般原則とおりです。
瑕疵担保責任の負担を軽減する特約
不動産売買契約では、瑕疵担保責任や契約不適合責任の「免責特約」を結ぶケースがあります。これは売主が負う責任を免除する特約です。ただし免責特約の締結には、以下の条件が課せられます。
- 売主が宅地建物取引業者(不動産会社)ではない
- 売主の知らなかった欠陥であること(売主が知って告げなかった場合には免責されません)
- 売主が故意に損害を発生させていないこと(売主が故意に発生させた損害については免責されません)
| 各法律における瑕疵担保責任の範囲と責任義務 | ||||
| 法律の種類 | 対象となるもの | 適用対象者 | 責任・権利の期間 | |
| 開始時点 | 期間 | |||
| 民法 | 売買の目的物 | 宅建法・品確法の規制を受けない 売主(個人など) |
不動産引渡し時 | 10年 |
| 買主 | 瑕疵を知った時点 | 1年以内に売主へ通知 5年以内に権利を実現 |
||
| 宅地建物 取引業法 |
建物または宅地 | 宅地建物取引業者である売主 | 不動産引渡し時 | 2年 |
| 買主 | 瑕疵を知った時点 | 1年以内に売主へ通知 | ||
| 品確法 | 新築住宅の 基本構造部分 |
新築住宅の 売主すべて |
不動産引渡し時 | 10年(20年まで延長可) |
| 買主 | 瑕疵を知った時点 | 1年以内に売主へ通知 | ||
ただし、瑕疵担保責任における免責特約がつねに有効であるとは限らず、民法では無効になる場合も規定されています。こういった場合、免責特約があっても買主は売主に責任追求できます。
瑕疵担保の責任を負わない免責特約も原則として有効ではありますが、以下に当てはまる場合は民法第572条で売主は瑕疵担保責任を免れることができないと定められています。
- 知りながら告げなかった事実に基づく責任(売主が欠陥を知っているのに買主に告げなかったケースです)
- 自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利に関する責任(売主が自ら第三者へ抵当権を設定したり物件を二重譲渡したりした場合の責任です)
隠れた瑕疵を見つけるポイント

瑕疵担保責任(契約不適合責任)では、一定期間売主が責任を負うこととなっています。責任追及できる期間は決まっていますから、隠れた瑕疵(不適合要因)を早く見つけることも重要です。また、購入契約を結ぶ前に見つけられれば、契約しないことで回避が可能です。ここでは、隠れた瑕疵(契約不適合要因)を事前に見つけるポイントをご紹介します。
商談時に担当者へ確認を取る
建物や敷地を確認しただけでは分からない欠陥があります。その代表的なものは前述した心理的瑕疵ですが、本来そのような物件は売主が瑕疵を買主に伝えた上で売買契約を結ぶ必要があります。担当者とじっくり打ち合わせを行い、念のためと前置きした上であらかじめ確認をしておくとよいでしょう。書面で「事件や事故は起こっていない」などと一筆差し入れてもらったり、契約書に「事故物件ではない」と記載してもらったりする方法もあります。
専門家に「建物状況調査」を依頼する
その建物がどのような状況か、専門調査を実施する「建物状況調査」を依頼して事前に確認する方法があります。建物状況調査とは、国に登録を受けた講習を修了している建築士によって行われ、建物の見えない劣化や構造上の変化などを確認できるものです。建物状況調査は売主へ依頼して手配してもらうこともできますが、買主自身が直接専門家(住宅診断を実施している建築事務所などの第三者機関)へ依頼して行ってもらってもかまいません。
商談から引渡しにかけて気を付けること

住宅を購入する場合、売主が不動産会社であることもよくあります。この場合、売主は一定期間瑕疵担保責任(契約不適合責任)を追わねばなりません。しかし、不動産会社がその期間を待たずに倒産してしまう可能性もゼロではありません。そうなってしまうと、責任を追及できなくなることも考えられます。
また売主が不動産会社ではなく個人の場合、負担軽減特約によって責任義務期間が短くなっているケースが多数です。
特に個人から中古物件を購入する場合は、売主としっかり打ち合わせの上物件をくまなく確認し、瑕疵の可能性を見つけておくことが大切です。建物状況調査(ホームインスペクション)により、建物がどのような状態か詳細確認した上で購入を決めることも1つの手でしょう。ホームインスペクションは「住宅診断」とも呼ばれ、実施している建築事務所や検査機関などへ依頼することができます。その際は、ホームインスペクションに関する資格を持つ診断士が在籍していることなどを目安に、信頼できる依頼先を選定しましょう。
ホームセキュリティの導入で防犯・防災対策を
家は末永く暮らすものですので、あとで不具合に悩まないよう慎重に計画を立てての購入が重要です。新居に住み始めてからのことを考え、積極的なセキュリティ対策も忘れずに検討しましょう。
ALSOKでは、個人の住宅向けホームセキュリティをご提供しています。お住まいになる住宅のスタイルに合わせ、最適な防犯・防災対策もしっかり行っておきましょう。
リーズナブルな価格でセキュリティ対策をしたい方はこちら
「ホームセキュリティ」 集合住宅にお住いの方はこちら(入居者個人で入れます)
「HOME ALSOKアパート・マンションプラン」
まとめ
住宅にはさまざまな「契約不適合要因(瑕疵)」があり、売買を行ってからそれらが見つかったときのために、売主は瑕疵担保責任(現在は契約不適合責任)を負う義務が課せられています。住み始めてから瑕疵に気づくことは避けたいものですし、できるだけ売買契約までの間に瑕疵の可能性を想定しながら物件を確認することが重要です。
十分な準備と確認を行い納得の上で家を購入し、その家をしっかり守るためのセキュリティ対策なども取り入れて、安心の新生活をスタートさせましょう。
監修者プロフィール

法律ライター 元弁護士
福谷陽子
弁護士であったときに得た法律知識や経験をもとに、法律メディアや法律事務所サイトにて精力的に記事の執筆監修を行っている。
法律問題ならどういった分野でも対応でき、不動産や契約等の企業法務、法律・判例解説などにも積極的に取り組んでいる。