AEDの価格相場や契約形態、費用を抑える補助金について解説
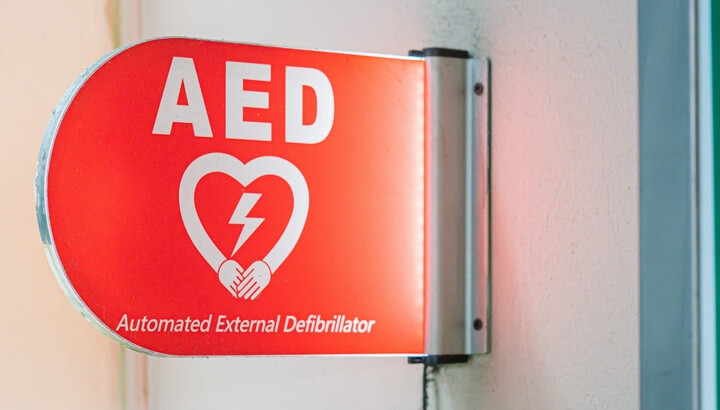
急な心疾患等によって「心室細動・心室頻拍」を起こして人が倒れたときに、適切な応急処置ができるよう、空港や駅、公共施設といった人が多く集まる場所を中心に、AED(自動体外式除細動器)が設置されています。万一、従業員やお客様が倒れてしまった場合に備えて、自社内や施設内にAEDの設置を検討している方も少なくないでしょう。
そこでこの記事では、AEDの契約形態や価格、設置に関する補助金・助成金についてご紹介します。
目次
AEDとは何か?仕組みと必要性
AEDとは「Automated External Defibrillator」の略称で、日本語では「自動体外式除細動器」と呼ばれます。急な心疾患によって発生する心室細動や心室頻拍といった不整脈に対し、電気ショックを与えることで心臓を正常な状態に戻すための機器です。突然人が倒れ、意識がない場合、心室細動・心室頻拍を起こしている可能性があります。AEDは、救急車の到着や病院へ搬送されるまでの間、救命措置を行うために使用される重要な医療機器です。
以前は、医療従事者だけが使用できましたが、2004年から一般の人でもAEDを使用して人命救助措置を行えるようになりました。音声ガイド機能や搭載した液晶ディスプレイで手順や操作方法を指示してくれるなど、初めて使う人でも適切に使用できるように設計されています。
出典:日本心臓財団「AEDって、何ですか?」
ALSOKの関連コラム
AEDの契約形態別の比較
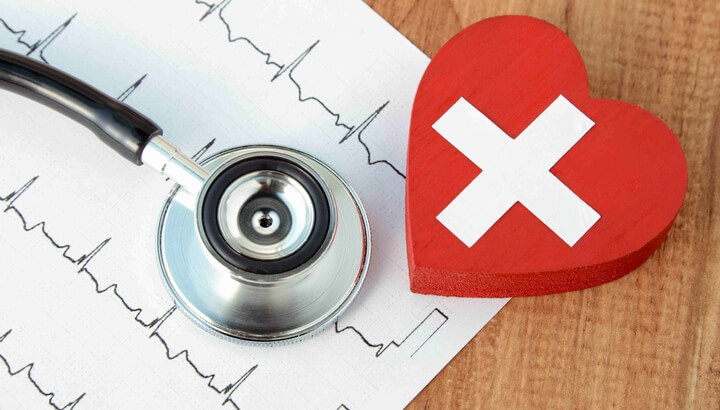
AEDを設置するには、購入のほかにレンタルやリースという手段があります。
ここではAEDの設置に際し、購入、レンタル、リース、それぞれのサービス内容の違い、メリット・デメリットについてご紹介します。
AEDを購入する場合
AEDは、各AEDメーカーおよび販売代理店などを通じて購入できます。AED本体のみを購入した場合は、バッテリーや電極パッドといった定期交換品を都度購入する必要があります。販売店によっては購入時に定期交換品に関するプランを選択できる場合もあるため、それらの活用もおすすめです。たとえば5年間定期交換品込みのプランを選択した場合、購入後5年間は定期交換品を新たに購入する必要はありません。
購入の場合、まとまった初期費用はかかりますが、ランニングコストを抑えられる点がメリットです。なお、AEDを購入した際の勘定科目は、取得価額に応じて固定資産として計上される場合と少額資産として計上される場合に分かれます。
AEDをレンタルする場合
AEDをレンタルする場合は、各AEDメーカーおよび販売代理店から直接レンタルします。
AEDをレンタルするメリットは、初期費用が抑えられる点と電極パッドなどの消耗品の定期交換、使用した消耗品の交換がレンタル料に含まれていることです。また、リース資産として資産計上されることなく、「賃貸リース料」として全額を費用計上できる点も経理上のメリットです。ただし、契約内容に関してはサービスごとに異なるため、機種、サービス内容、料金を確認しましょう。
一方で、レンタルのデメリットとしては、中途解約した場合に解約金が発生することや、販売店によっては本体が新品ではない可能性があることが挙げられます。また、長期にわたってAEDを契約する場合、総額が購入した場合よりも割高になることがあります。
AEDをリースする場合
リースの場合、レンタルの場合と特徴やメリット・デメリットはあまり変わりません。リースは利用者と販売店をリース会社が仲介しての三者間契約になるため、利用者と販売店の二者間契約であるレンタルとはその点が異なります。
リース契約では、一般的に商品の購入金額をユーザーが決め、その上でリース会社がリース料率を設定し、毎月のリース料金が決まります。サービスによってはさまざまなオプションを付加することも可能です。また、動産総合保険がついている場合も多いため、天災や盗難に関しても補償されています。ただし、契約期間中の途中解約や買い取りが不可能な場合があります。なお、リースで取り扱われるAEDは基本的にすべて新品です。
また、会計処理は金融商品取引法適用会社か否か、資本金や負債総額による規模、業種によって異なりますが、「賃貸リース料」として費用計上される場合と、「リース資産」として資産計上される場合に分かれます。
ALSOKのAEDはこちら
ALSOKの関連商品
AEDの設置にかかる費用・価格
AEDを設置する場合、どのくらいの費用がかかるのでしょうか。ここでは、購入・レンタル・リースそれぞれの場合にかかる費用の目安を解説します。
初期費用・購入費用
AEDを購入する場合、初期費用としてAED本体の購入代金が発生します。AEDの本体代は一般の人が使用できるものであれば約20~50万円が相場です。このほかに、付帯設備費用として壁掛け用ブラケットの設置工事費や、AED収納ボックス代、キャビネット代、設置場所を示す看板代などの費用が発生することもあります。
なお、レンタルやリースの場合、基本的に初期費用は発生しませんが、設置環境やオプションによって初期費用がかかる場合があります。
レンタル・リース料
AEDをレンタル・リースする場合、月額4,500~9,000円が相場です。レンタル・リースは基本的に5年契約となるため、総額で27~54万円かかります。
総額で考えると購入するよりも高く感じるかもしれません。しかし、レンタル・リース料には消耗品の交換費用が含まれていることが多く、実際にAEDを使用した際も追加費用が発生しにくいという安心感があります。
消耗品の交換費用
AEDに付属しているバッテリーや電極パッドは、未使用であっても交換時期を迎えたら新しいものと交換しなければなりません。そのため、AEDを購入する場合、初期費用に加えて消耗品の定期交換費用が別途発生することがあります。部品の交換費用の相場は、下記のとおりです。
- バッテリー(約4年で交換):約3~4万円
- 電極パッド(約2年で交換):約1万円
AEDを購入する場合、保証期間中(5年間)にバッテリーは1個、電極パッドは2個交換する計算です。そのため、初期費用を合わせるとトータルで32~60万円の費用が発生します。また、電極パッドの再利用はできないため、AEDを使用するたびに新しいものを購入する必要があります。
なお、購入の場合も、消耗品の交換を含めたプランが用意されていることもあります。プラン内容を確認してから購入することをおすすめします。
講習費用
AEDは、ただ設置するだけではなく、緊急時に適切に使用できるよう事前に講習を受けておくことも重要です。講習は、消防署の無料講習や日本赤十字社の有料講習、民間団体による企業向け出張講習などがあります。講習の種類によっては、講師派遣費や教材費が発生することがあるため、AEDの導入に必要な費用として見込んでおきましょう。
ALSOKの関連商品
AED購入時の補助金・助成金の活用方法

AEDを設置する際、費用負担を軽減する方法として、補助金制度や助成金制度を活用できる場合があります。ここでは、AEDに関する補助金や助成金の種類や対象、申請方法をご紹介します。
補助金・助成金の種類
AEDに関する補助金や助成金はおもに2つの種類があります。1つ目は、各地方自治体が設けている公的な補助金や助成金、2つ目は事業財団などが実施している自治体以外の助成金です。
自治体の補助金制度
地方自治体の補助金や助成金は、都道府県単位ではなく市区町村単位で設けられているケースがほとんどです。補助率は1/2~2/3程度で、各自治体により補助率が異なります。たとえば東京都大田区では、AEDの購入・設置に際し、初期費用などの1/2を補助しています。
事業財団の補助金制度
地方自治体以外にも、事業財団が独自にAEDの設置にかかる費用の補助をしている場合もあります。たとえば、日本スポーツ振興センターではスポーツ団体向けに、自治総合センターでは地域団体向けに、あんしん財団では中小企業向けの補助金・助成金制度を設けています。事業財団による補助金・助成金制度は、対象となる団体・企業が限定されているため、事前に確認しておきましょう。
補助金・助成金の対象先
AED設置による補助金・助成金の対象となるおもな組織や団体は下記のとおりです。
- 自治会
- 自主防災組織
- 商店街
- 保育園・幼稚園
- スポーツ団体
- 老人クラブ
各企業や団体なども対象に含まれますが、地方自治体の補助金・助成金では保育園や自治会、消防団などの防災組織、商店街などが認可されやすいとされています。ただし、「消費税の確定申告義務がある団体」と「町会や自治会等の消費税の確定申告義務がない団体」で補助金額は異なります。
また、事業財団による補助金・助成金は財団が取り組む事業内容に即した活動を行っている団体がおもな対象です。
補助金・助成金の申請方法
AEDの設置を推進するため、単独で補助金・助成金制度を設けている自治体や事業団体もあれば、「防災設備」の一環として補助金・助成金を設けている自治体もあります。以下では、AED設置に関する補助金の申請方法を3つのステップでご紹介しています。詳しい申請方法は、補助金・助成金制度を設けている自治体や団体の公式サイトで確認できます。
申請書類準備
まずは、申請に必要な書類を用意しましょう。設置予定場所の詳細図面や、施設の利用者数・設置理由を明記した計画書、AED機器の見積書、団体の定款や登記簿謄本などの組織証明書類が必要になります。利用する補助金・助成金制度によって必要な書類が異なるため、必ず確認するようにしましょう。
申請・審査
窓口に申請書類を提出すると、補助金の交付要件を満たしているかどうかが審査されます。設置場所は適切か、利用者への効果、維持管理体制などが評価項目です。結果は書面で通知され、承認後に交付決定通知書が発行されます。
設置・報告
補助金の交付が決まったら、AEDを購入・設置し、完了報告書を提出します。設置の報告には、領収書や設置写真、保守契約書の写しなどの添付が必要になることがあります。
・AED単独で補助金・助成金を設けているケース
出典:24時間AED設置補助事業について(東京都大田区)
https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/hoken/iryokikan_hoka/aed/24th-aed.html
・防災設備の一環として補助金・助成金を設けているケース
出典:防災資機材購入補助(福井県福井市)
https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/bosai/bosai/sikizaihozyo.html
補助金を申請する際の注意点
AEDの設置にあたり補助金制度を活用する場合の注意点をお伝えします。
購入前の申請を厳守する
補助金を受けられるのは、AEDを購入する前です。購入後の申請は補助金の対象外となるため、必ず購入前に申請しましょう。
また、多くの自治体では予算の都合上、申請期限や募集期間を設定しています。年度初めに募集が開始され、先着順で受付が行われるケースが一般的です。そのため、申請前に自治体などの公式サイトを確認し、申請期限や募集期限が過ぎていないかをチェックしましょう。
対象要件を満たしているか確認する
補助金制度によっては、対象となる施設や団体に関するさまざまな要件が設けられています。補助金を申請する場合は、事前に自治体や団体の公式サイトなどで受給資格を満たすか確認しましょう。
おもな要件の例として、以下のようなものが挙げられます。
・営利企業:多くの自治体では営利企業を対象外
・従業員数による制限:中小企業など、一定規模以下の事業所に限定
・設置場所の制限:24時間アクセス可能な場所
・既存AEDの有無:すでにAEDを設置している場合は対象外
ALSOKのAEDサービスは導入から管理・講習までをトータルサポート

AEDは一般の人が使用できる救命措置のための重要な医療機器です。人が多く集まる場所や建物には必需品といえます。
そこでおすすめなのがALSOKのAED販売・レンタルサービスです。警備会社のノウハウを活かした独自の管理システムで、AED本体の耐用期間や消耗品の交換時期を管理します。そのため、いざという時に安心してAEDをお使いいただくことが可能です。
購入・レンタル・リースそれぞれに対応しており、さまざまな用途や設置環境に合わせたラインナップを揃えております。
また、導入・設置するだけではなく、スタッフ・従業員が迷いなく使用できるよう使い方を学ぶことも大切です。AEDの使い方が分からないという場合には、心肺蘇生法やAEDの使用方法の講習も実施しております。
ALSOKでは、導入から管理、講習までを総合的に支援しておりますので、AEDの設置を考えている場合は、ぜひご相談ください。
ALSOKのAEDについて詳しくはこちら
ALSOKの関連商品
まとめ
AEDが必要となる場面は、いつ訪れるか分かりません。突然の心停止など、緊急時に居合わせた人(バイスタンダー)が迅速に対応できるかどうかが、命を救う大きな分かれ道になります。
これまで医療従事者に限られていたAEDの使用も、現在では一般の人でも操作が可能となり、公共の場や民間施設への設置が広がっています。設置は義務ではないものの、多くの人が出入りする施設やオフィスでは、いざという時の備えとして有効であり、今後もAEDの設置の波は広がっていくと考えられます。AEDの設置を検討している場合は、受けられる補助金制度もあわせて確認し、万全の状態を整えて安心して過ごせる職場環境を整備しておきましょう。















