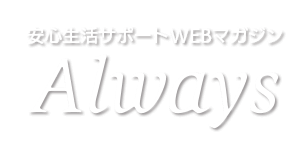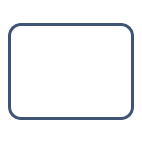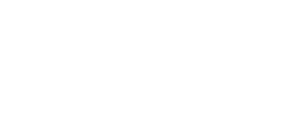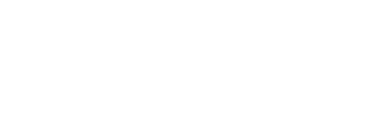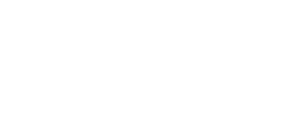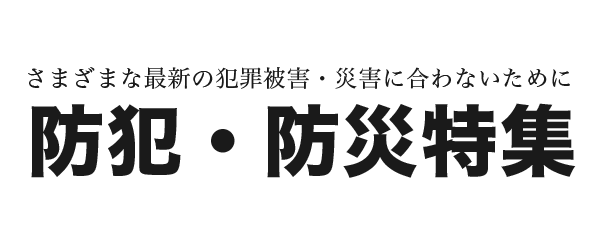
自分と家族を守ろう
今日から備える大規模災害
台風や豪雨による水害も他人ごとではありません。
自分と大事な人を守るために、大災害が起きたときの行動をシミュレーションしておきましょう。

大規模災害、備えあれば憂いなし
2011年の東日本大震災から14年。その間に、熊本地震(2016年)や能登半島地震(2024年)など、震度6強以上の大地震が全国各地で起こっています。さらに、30年以内に発生する可能性のある大地震として、南海トラフ大地震、首都直下型地震が予測されており、日本中の不安が高まっています。
最近では、夏場の大雨の頻度が増しており、河川の氾濫や浸水被害が毎年のように報告されています。最大風速が45m/s以上の非常に強い熱帯低気圧(台風)の出現数は増加傾向にあるとされており、災害の激化が懸念されています。
災害の瞬間は、どんなに冷静な人でもパニックを起こし、思う通りには動けないもの。災害直後にどう動くべきか、シミュレーションしておくことが大切です。大地震と台風・豪雨では、備え方も異なります。自分はどう立ち回るべきかを考え、家族と共有しておくようにしましょう。
とっさの判断が身を守る 大地震
地震発生、その瞬間は命を最優先に
緊急地震速報のアラートが鳴ったら、身を守る・つかまる・危険から離れるの3つを念頭に行動します。頑丈な机の下などにもぐったり、うつぶせになって両手で頭を覆う「ダンゴムシのポーズ」をとるなどの防御を。

揺れがおさまったら確認作業
①室内の安全を確認
ガラスなどが散乱している場合があるので、靴や厚底スリッパを履きましょう。
②出口を確保
いつでも避難できるよう、ドアや窓を開けておく。後から開かなくなることも。
③火の元を確認
調理器具や暖房器具、ガス器具は、揺れがおさまってから落ち着いて消す。小さな火は消火し、炎が天井に届くなど身の危険を感じたらすぐに避難。
被害状況を見て安全な場所へ
地震がおさまったら、避難の必要があるか判断します。津波や火災、建物崩壊などの危険がある場合は、「一時避難場所」や「広域避難場所」へ。危険がなくなったら、家の被害状況を詳しく見て、自宅で過ごせない場合は学校や公民館などの「避難所」か、親せきや知人宅へ。1週間、支援なしで過ごせるようなら「在宅避難」を選びましょう。
一時避難場所
身の安全を確保するため、一時的に避難する場所。さらに避難が必要な場合は、「広域避難場所」へ移動することも。

避難所
一定の期間滞在するための場所。体育館や公民館が多い。

「うちは大丈夫」が最も危険 台風・集中豪雨
①気象情報をこまめにチェック
台風や豪雨は、気象庁がある程度予測し、情報発信しています。あらかじめよく調べておくことが大切です。
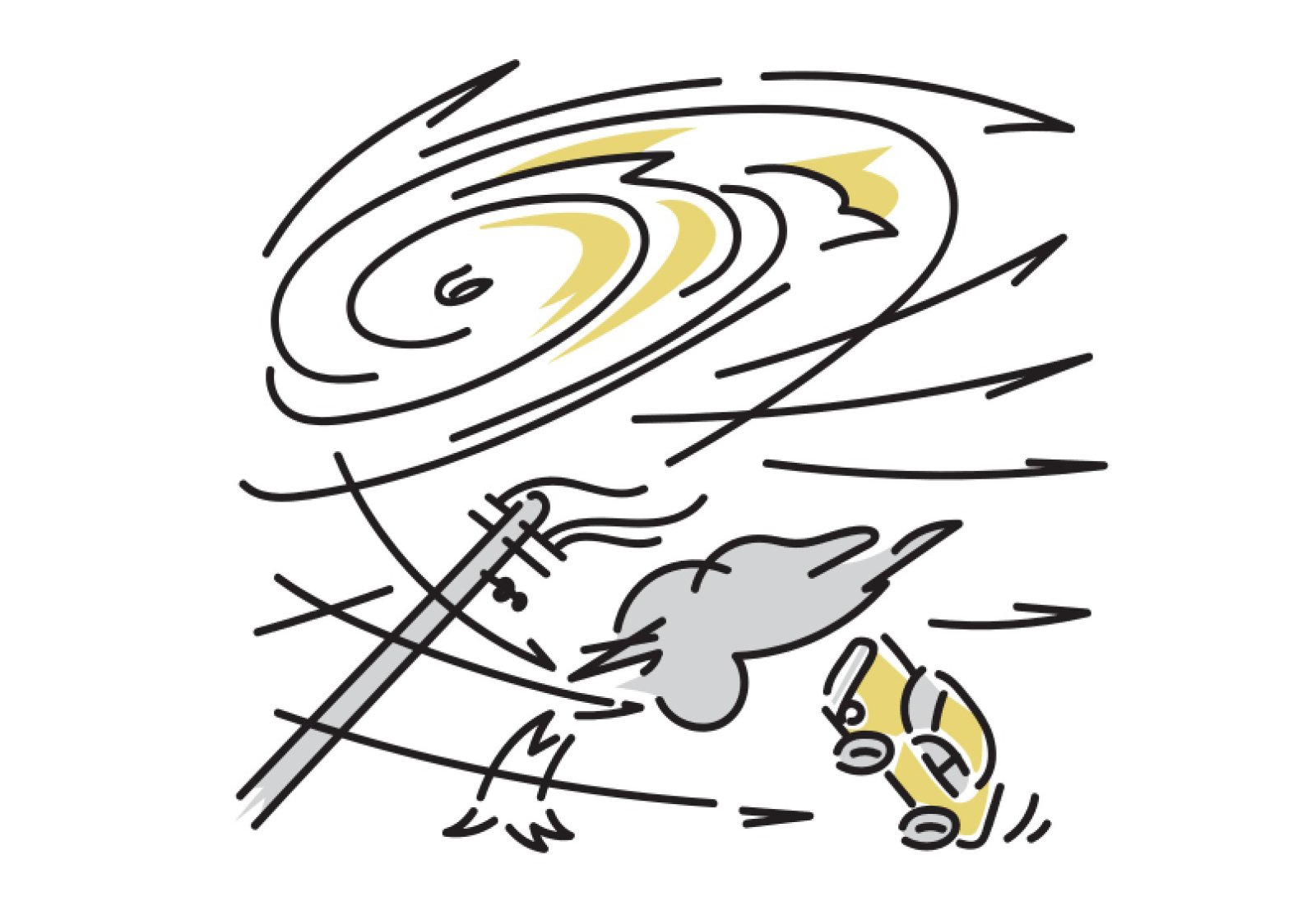
②ハザードマップを確認
自治体が作成したハザードマップには、がけ崩れや地滑り、洪水などの地域の持つリスクが示されています。自分のいる場所の周辺で想定される危険を、チェックしておきましょう。避難場所や避難経路が載っている防災マップも活用しましょう。
③避難をためらわない
風水害や土砂災害の危険が迫っている場合は、自治体が避難指示を発令します。発令される前でも、危険を感じたら避難を開始します。

警戒レベル4までに避難しよう
自治体が発表する避難情報や防災気象情報。とくに、警戒レベル4の避難指示が発令された場合は、速やかに避難を開始することが必要です。
警戒レベル5 緊急安全確保
安全な避難ができず、命が危険な状況。この発令を待たずに避難を。
警戒レベル4 避難指示
危険な場所から全員避難します。
警戒レベル3 高齢者等避難
避難に時間がかかる高齢者や障がい者、幼い子どもなどは、その支援者と避難します。
警戒レベル2 大雨・洪水・高潮注意報
自分の避難行動を確認します。
警戒レベル1 早期注意情報(警報級の可能性)
災害への心構えを高めます。
スマホを防災アイテムに! 防災アプリ8選
災害時にも大活躍するスマホ。
安否確認や情報収集が手早く行える必須アイテムです。 バッテリーが長持ちするよう、普段からまめに充電し、充電器も持ち歩くようにしましょう。
災害時には無料のWi―Fi「00000JAPAN」が開放されるので、通信会社の通信が途絶えた場合にもネットにつなぐことが可能です。
災害時に役立つ8つのアプリを活用して、スマホを防災アイテムにしておきましょう。
- 自治体の防災アプリ
- 東京都の防災アプリ
- ラジオアプリ □ 災害情報アプリ
- 位置情報を発信するアプリ
- SNSアプリ
- 応急手当アプリ
- 天気アプリ
※これらをまとめた「防災フォルダ」をつくっておくと便利です。