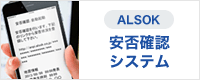七五三はいつ祝う?年齢やお参りの時期について

子どもの健やかな成長を祝う「七五三」。はじめてお子さんを迎えた方は、いつ七五三を行うべきなのか?決まりはあるのか?など疑問も多いのではないでしょうか。そこで今回は、七五三のお祝い時期や年齢についてご紹介します。
目次
七五三の意味や由来とは?
七五三は、お子さまの健やかな成長を祝い、祈願する行事です。
その名の通り3歳、5歳、7歳で行われます。それぞれの年齢の儀式は名称や意味が異なり、男女で儀式をする年齢も異なります。
七五三の由来となった記念行事

七五三の由来となった記念行事は、3歳「髪置の儀」5歳「袴着の儀」7歳「帯解の儀」です。この行事について詳しく見ていきましょう。
髪置の儀(かみおきのぎ)
髪置の儀は、髪を伸ばし始める3歳の男女に行われていた行事です。糸で作った綿白髪を頭に乗せて長寿を祈願していました。これは、髪に白髪が生えるまで生きてほしいという親の願いでもあったそうです。
平安時代は、3歳までの子どもは性別問わず頭を坊主にする習慣があったため、髪を伸ばし始めるということはここまで無事に成長できた証でもありました。
袴着の儀(はかまぎのぎ)
袴着の儀は、子どもがはじめて袴を着る行事で、着袴(ちゃっこ)とも呼ばれていました。男女に関係なく5~7歳までの子どもに行っていましたが、江戸時代以降は男の子だけに執り行われるようになったのです。天下取りの意味を持つ基盤の上に立って吉方に向き、縁起の良いとされていた左足から袴を履く儀式を行っていました。
帯解の儀(おびときのぎ)
鎌倉時代に行われていた、紐で着付けていた子どもがはじめて帯を締める成長の儀が、室町時代に帯解の儀として制定されました。当時は、9歳の男女に行われていたそうです。
そして、江戸時代に5歳の男の子は「袴着の儀」を、7歳の女の子は「帯解の儀」を行う形になりました。この帯解を経て大人の女性へ歩み始めると考えられていたようです。
七五三のお祝いをするのはいつ?すぐわかる年齢早見表!

七五三は、男女でお祝いをする年齢が違います。男の子と女の子に分けて、七五三をお祝いする年齢をあらためてご紹介します。
2024年~2027年の七五三年齢早見表
| 男女ともに対象 | 男児のみ対象 | 女児のみ対象 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3歳(数え年) | 3歳(満年齢) | 5歳(数え年) | 5歳(満年齢) | 7歳(数え年) | 7歳(満年齢) | |
| 2024年 (令和6年) |
2022年 (令和4年) 生まれ |
2021年 (令和3年) 生まれ |
2020年 (令和2年) 生まれ |
2019年 (令和元年) 生まれ |
2018年 (平成30年) 生まれ |
2017年 (平成29年) 生まれ |
| 2025年 (令和7年) |
2023年 (令和5年) 生まれ |
2022年 (令和4年) 生まれ |
2021年 (令和3年) 生まれ |
2020年 (令和2年) 生まれ |
2019年 (令和元年) 生まれ |
2018年 (平成30年) 生まれ |
| 2026年 (令和8年) |
2024年 (令和6年) 生まれ |
2023年 (令和5年) 生まれ |
2022年 (令和4年) 生まれ |
2021年 (令和3年) 生まれ |
2020年 (令和2年) 生まれ |
2019年 (令和元年) 生まれ |
| 2027年 (令和9年) |
2025年 (令和7年) 生まれ |
2024年 (令和6年) 生まれ |
2023年 (令和5年) 生まれ |
2022年 (令和4年) 生まれ |
2021年 (令和3年) 生まれ |
2020年 (令和2年) 生まれ |
上図が2024年から2027年の七五三年齢早見表です。
男の子は3歳と5歳
男の子の場合は、3歳と5歳のときに七五三のお祝いをします。髪置の儀で祝うのは3歳の男女、袴着の儀は5歳の男の子だったことから、3歳と5歳のときに七五三を行うのが一般的です。
ただし、地域や家庭によっては3歳のお祝いは行わず、5歳のみの場合もあります。
女の子は3歳と7歳
女の子の場合も男の子と同様に3歳のときに七五三を行います。そして、男の子と異なるのが女の子の場合、3歳の次は7歳と4年ほど間があくことがあります。これは、女の子が7歳のときに行われる「帯解の儀」から来ています。
早生まれの場合
1月1日~4月1日に生まれた早生まれの子の場合、「いつ七五三のお祝いをすれば良いのか」と迷う方もいらっしゃるでしょう。特に決まりはないため、年齢・学年どちらでお祝いしても良いです。
学年に合わせてお祝いすると和装や神社での儀式中待ち時間に耐えられなかったり、トイレトレーニング中でトイレに不安があったりするかもしれません。そのため、七五三はお子さんの成長に合わせて行うことをおすすめします。
「数え年」と「満年齢」の違い

年の数え方には、数え年と満年齢があります。ここでは数え歳と満年齢の違いについてご紹介します。
暦年の個数で加齢するのが数え年
生まれた瞬間から1歳として、年を越した1月1日を迎えると1つ年をとるという数え方です。例えば、2020年4月に生まれた子の場合、生まれた時点で1歳とし、2022年1月になると3歳と数えるということです。数え年は、「現在の西暦-生まれた年の西暦+1」で算出することができます。
昔は満年齢ではなく、この数え年で年齢を数えるのが一般的でした。そのため、数え年で七五三をしたほうが良いと両親や祖父母など周囲にアドバイスされる方もいるでしょう。
しかし、数え年で祝う場合、生まれた時期によっては満年齢2歳のときに七五三をすることになります。七五三をする年齢に決まりはないため、子どもの成長や体調に合わせてお参りするのがおすすめです。
誕生日で加齢するのが満年齢
満年齢は、生まれたときは0歳として、誕生日を迎えるごとに1つ年をとるという数え方です。3歳であれば、誕生日の前日までは2歳、誕生日を迎えると3歳になります。
現在では、満年齢での年の数え方が一般的なため、なじみのある数え方です。
おすすめのお参り時期はいつ?

七五三の日は、「11月15日」です。そのため、この日にお祝いするのが一般的。しかし、平日であったり、当日は混雑していたりするため、日付をずらしてお参りする方も多くいます。
11月15日前後でお参りする日を決めると良いでしょう。
また、七五三のお参りを行う日として、「六曜」を参考にして決める方も多くいます。
六曜とは、その日の吉凶や運勢を表す暦注のこと。「先勝」「友引」「先負」「仏滅」「大安」「赤口」の6つあります。中でも「大安」は1日中「吉」とされ縁起が良いため、お祝いごとに向いている日とされています。他の日も、時間帯によっては吉の場合もあります。
七五三に適した服装は?

着物や袴、ワンピース、スーツなど七五三で着用する服装にはさまざまな種類があります。服装に決まりはないものの、3歳では長時間着物を着用していることが難しい場合や、活発なお子さまも多いため、和装ではなく洋装にしたいと考えているママパパも多いでしょう。最近では、七五三のお参りでは洋装、記念撮影では和装というケースも多く見られます。
【七五三】和装の場合
和装には独特のきまりごともあるため、衣装を準備する前に基本を確認しておきましょう。
男の子の和装

右:3歳の男の子 左:5歳の男の子
男の子の七五三和装の組み合わせは以下です。
| 3歳の男の子 | 着物(一つ身または三つ身)と被布 |
|---|---|
| 5歳の男の子 | 着物(三つ身)と羽織・袴 |
伝統に沿う場合は、5歳からは羽織・袴スタイルが一般的です。
ただし、3歳で袴を着用しても特に問題はありません。着物はお子さまの体型に合わせて、事前に肩上げや腰上げをしておく必要があります。
女の子の和装

右:3歳の女の子 左:7歳の女の子
女の子の和装は、着物に被布を合わせたスタイル、もしくは帯で締める着物スタイルが一般的です。お子さまが小さい3歳の七五三は、締め付けが少ない被布を着用することが多いようです。ただし、厳密な決まりはないため、3歳で帯を締めるスタイルを選択しても問題はありません。
| 3歳の女の子 | 着物(一つ身または三つ身)と被布 |
|---|---|
| 7歳の女の子 | 着物(四つ身)と帯 |
着物はお子さまの体型に合わせて肩上げや腰上げをした方が良い場合があります。
被布や帯は必ずしも着物と同色にする必要はなく、色合いを変えることでコーディネートの幅を広げられます。お子さまのお気に入りの組み合わせを見つけても良いですね。
【七五三】洋装の場合
神社やお寺での参拝やお祝いの食事会には、動きやすく、汚れた際に手入れをしやすい洋装を選ぶご家庭も多いです。洋装を選ぶ際に注意したいのが、洋装であってもふさわしい装いをしないと失礼になってしまう点が挙げられます。
男の子の洋装

七五三の男の子の洋装ではスーツやジャケット、パンツといったフォーマルなスタイルが定番です。スーツなどは入園式や入学式などにも使いまわすことができます。スーツの色は一般的に黒や紺、ネイビーです。パパとお揃いのジャケットや同じ色のネクタイなど、テイストを合わせたおしゃれな装いをするのも良いでしょう。
動きやすく、お手入れも簡単であるため、特に活発な3歳の七五三で洋装を選ぶ方も多いようです。
女の子の洋装

七五三の女の子の洋装では華やかなワンピースやドレスを着用するのが定番です。移動や食事会がある七五三当日には丈が比較的短いワンピースで、記念写真ではプリンセスのようなロングドレスと衣装を変更するケースも多く見られます。女の子の場合、色やデザインなど好みがはっきりしているお子さまもいるでしょう。
洋装の場合は、着物ほど高額ではなく普段着としても使いまわすことができるため、お子さまと好きなデザインを選ぶ楽しみもあります。
ご両親の服装
和装の場合

七五三の場合には、訪問着や色無地(一つ紋か無紋)、付け下げなどが適しています。格の高い黒留袖や色留袖、カジュアルな印象を与える小紋や紬などは不向きです。
お子さまが女の子の場合には主役のお子さまを引き立てるよう控えめな色柄を選びましょう。男の子の場合は渋めの色合いが多いため、ママの着物は少し華やかなものを選んでも良いでしょう。
お子さまとママが和装である場合、パパも和装で合わせると統一感が出ます。
パパが和装の場合もママと同様にお子さまを引き立てるような着物を選ぶことがポイント。お子さまより格の高い黒紋付の羽織・袴や普段着感覚のウールは避けましょう。一般的にパパの和装は羽織袴を選ぶ方が多い傾向にあります。また、足元は白足袋が無難です。
洋装の場合

ママの洋装は、お祝いの席なのでブラックフォーマルではなく、セットアップのスーツや上品なワンピースなど華やかさの感じられるものがおすすめです。
ただし、ノースリーブやミニスカートなど、肌の露出が多いものは避けましょう。アクセサリーやバックなどはセミフォーマルなデザインで色柄はやや控えめなものを選ぶと全体が上品にまとまります。
なお、ご祈祷の場合は必ずストッキングを着用しましょう。
パパの洋装はスーツが一般的です。ビジネススーツでも問題はありません。黒やダークグレーといった落ち着いた色味のスーツに、シャツやネクタイなどの小物でおしゃれ感を出すのがおすすめ。最近では、ジャケットにパンツといったカジュアルな装いも見られます。お子さまやママの衣装とのバランスも大切なので、ご家族で話し合うと良いでしょう。
多様化する七五三の祝い方

近年、七五三のお祝いは多様化しています。これは、家庭の事情がさまざまであることや、年齢などに絶対的な決まりがないため。さらに、2020年以降は感染症対策として混雑を避けるといった理由も加味され、昔ながらの行事である七五三も変わってきているようです。
兄弟・姉妹で一緒にまとめてお祝いする
兄弟・姉妹がいる場合は、同時に行う方もいます。満年齢では2歳だけど、7歳のお姉ちゃんがいる、5歳のお兄ちゃんがいる関係で一緒に七五三のお祝いをするといったケースです。
写真は前撮り
昔であれば、お祝い事の際はお参りの当日に記念撮影することがほとんどでした。しかし、着付け、お参り、写真撮影、食事会と当日は忙しくなるため、子どもが集中できなかったり、疲れてぐずったりしてしまう可能性があります。撮影とお参りは分けて写真は前撮りにすることで、余裕のあるスケジュールを立てることができます。
仕事の調整が必要になりますが、混雑を避け平日に前撮りをするのも感染症対策や子どもの機嫌を考慮するとおすすめです。
お参りの時期をずらす
大勢の人が集まるところは感染症拡大のリスクがあるため、混雑するような場所は避けたいのが本音という方は多いでしょう。その場合、11月ではなくその前後の10月や12月にお参りの時期をずらす、ご祈祷をする場合は事前予約をして行くといった対策ができます。
子どもの成長とともに防犯対策もしよう
七五三は、子どもの成長を祝う節目の時期です。特に7歳の時期は、小学校に入学している年齢です。共働きのご家庭であれば、子どもが留守番をする機会が多くなるでしょう。子どもに留守番をさせる不安とともに家の防犯が気になるという方も多いのではないでしょうか。
こうした節目の時期に、防犯対策についてもしっかりと考えていきましょう。
ALSOKでは、家の防犯対策や子どもを見守るサービスを提供しています。
ALSOKのホームセキュリティは、不審者侵入の検知や火災、緊急時などにガードマンがかけつけるサービスです。子どもでも簡単に操作できるため、留守番中に万が一の事態が起こった場合の安心につながります。
また、登下校時の安全も気になる方には、お子さまに持たせられる「まもるっく」がおすすめです。まもるっくは、GPSを搭載した携帯端末。ストラップを引くことで防犯ブザーが鳴り、ALSOKへ緊急通話が可能です。危険なことがあれば、必要に応じてガードマンが駆けつけます。それだけではなく、お子さまの居場所を確認したり通話によって帰宅を促したりすることもできます。
ALSOK関連コラム紹介
まとめ
今回は、七五三のお祝いをする年齢やお参り時期についてご紹介しました。
男の子は3歳と5歳のとき、女の子は3歳と7歳のときに七五三のお祝いをするのが一般的です。しかし、地域や家庭の事情によって異なることもあります。決まりはないため、子どもの成長や体調に合わせて決めると良いでしょう。